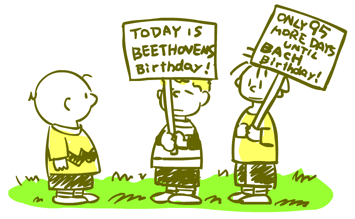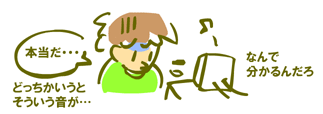-
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
実は、この年まで「モーツァルトがいい」と思ったことが
いっぺんもなくて(おいおい)、
世間の”生誕何周年フェア~”なんてのも
「フッ」って思っていましたし、
”モーツァルトと聴くと頭が良くなる!”なんてのも
「バッハの方がいいよ絶対」と
憤慨していたくちでした。
(シュローダーの服の色忘れました)
だけど、おとといあたり? たまたまついていたテレビで
たいへんいい感じの素敵な曲を指揮者がふっていたので、
わーなんの曲だろう?
と思ったら、モーツァルトの交響曲39番だったのでした。
その時の衝撃と来たら、もう、
じゃがいもと思って掘っていたのがピクルスが出てきちゃったような感じ。(どういう感じだ)
で、さっそくアマゾンで、カール・ベームさん指揮のモーツァルトのCDを買ってしまいました。
初モーツァルトCD。
我ながらびっくりです。
でも同時に収録されていた36番は、やっぱり全然ぴんとこないです。
39番が、妙に訴えてくるのです。不思議。
うーん。といいつつ、38番の<プラハ>もわりと好きかな・・・。(長年のモーツァルト嫌いはどうした)PR -
このあいだ、はじめて「のだめ」のアニメを見ました(偶然)
楽器の演奏の再現度がすごいですね。
ちょうどラフマニノフのピアノ協奏曲2番を
千秋が弾いてるとこでした。
ラフマニノフの2番は、あの、
♪だーら だーら だーら らららー
っていう地の底をはうような1楽章も
おっかなくて面白いけど、
3楽章のラスト直前の、荘厳なしらべが
オーケストラで堂々とやってくるところが
一番好きです。
千秋も3楽章から弾いてくれたらよかったのに。(無茶言うな)
1楽章は出だしがトロールの行進(しかも学徒動員された)みたいで
ちょっと恐い。
どう聴いてもそのあと屍累々な状況になってるし。
3楽章になるとピクシーがいっぱい飛んでて好きです(?)
ちなみにラフマニノフのピアノ協奏曲の2番は、
チャイコフスキーの1番とセットになっているリヒテル(ピアノ)とカラヤン(指揮)のCDで
いつも聴いてます。
1959年の演奏で、しみじみ。
ただ、ラフマニノフの3楽章の余韻にひたる間もなく、
チャイコフスキーの1楽章が「お邪魔しマース」とやってくるのが
おかしさ爆発です。 -
ミニ発表会がおわりました。
今回は、「ボーカルクラス」と”連弾組”(3人連弾と2人連弾)の
第2部に入ってました。
(1部と3部はクラシックなど)
そしてー
実は今回、ここからもリンクさせて頂いてる
takaiさんの、ピアノ曲「白い花」を
弾いてきたのでした!
すみません、私、弾く曲について事前に書くとうまく弾けなくなる・・・かも? という
変なジンクスがあって
今頃公表です。
1度書いたのも非公開にしてたりしました、実は(笑)
「白い花」はとってもきれいな曲で、始めて聞いた時から大好きだったので
一度弾いてみたいなと思っていたんです。
で、急に(←いつものこと)ミニ発表会に出ることになり、
takaiさんにお伺いして、快諾のうえ応援までしていただき(takaiさんありがとうございました!)
翌週のレッスンでさっそく言ってみたのでした。
そのうえ(笑)
1発で突っ込まれ~
何故か分からないけど、先生には
曲の本来の姿が分かるらしい。
(1回聞いただけで)
そして、
この瞬間から、難易度Cぐらいかなーと思っていた曲が、
難易度Eになったのでした。
-----
でも、先生もバッハよりこちらの方が
ずっといい!と言ってくださったし、
弾かないわけにはいかないのです!
離れた和音を分離して弾くよう言われたわけですが、
そこはよほど気をつけないと、音を外す。
(日頃の練習不足のせい。)
「音を外さないよう気をつける」というのは、頭でやることですが、
「うたうように弾く」というのは、心でやることです。
頭で弾いてると音楽にならないし、
心で弾いてると音を外す。
このジレンマで一時はどうなることかと思いました。
で、心で弾けるようになったのが
前日の練習の最後の1回。
(と、翌日の朝弾いた2回。)
運が良かったとしか言えません。
しかも、その夜寝ている時、うつらうつらしながら
ずっと分からなかったところがどう弾いたらいいのか聞こえました。
☆
で、ようやく今日の話ですね(笑)
奇跡的にといおうかみなさんありがとうというか
だいぶん変な弾きようでしたが
とにかく今までで1番ぐらいよく弾けました。
ちょっとまた足ががくがくしたけど(何故だ)
それに、(案の定)たいへん好評で
みなさん、歌詞のある曲のようですね、とか
どなたの曲ですか? とか
素敵な曲ですねえ、きれいですね、と
たいへん楽しんでいただけたのでした。
いや演奏がじゃなくて曲を・ですよ。もちろんー(笑)
でもまあ挑戦しがいのある山(?)でした。
日頃の基礎練習の足りなさも身にしみたし。
先生にも言われたし(↑)
明日からクラマー・ビューローです。
takaiさんほんとにありがとうございました! -
私は譜読みが大変苦手です。
あんまり時間がかかるんで、
最近は意識的にがんばって(自分的には)速めに読みましょう月間を
やっていました。
が。
そうするとどうも機械的に読んでしまうらしい。
「楽譜に書いてあるから、こう弾く」
みたいな。
どうもそれじゃ違うらしいのですよ。
楽譜、特に楽譜記号はいわば標識で、「ここから○○市」と書いてあるから、そこが○○市になるんじゃなく、
○○市に行こうと思って車を走らせていたら、「ここから○○市」と書いてあって、
ああ進路は間違ってなかったんだな。みたいな。
うまく言えないんですが・・・。
楽譜にfと書いてあるからfにしたってだめなのですよ。
こんな流れがきもちいい、と音を大きく盛り上げていったら、
そのさきに「f」とあって、「やっぱりね」みたいな。
そうやっていって、始めて自分の演奏に近づく気がします。
機械的にfにしたってだめらしいのです。
もっとも、そうやって盛り上げていったら、
その先に「p」と書いてあって「?」と思うこともあるけど
そういう時は、その前とか、その8小節前とか、
そもそも始めの小節とかの、弾き方が違っているのです。
たぶん。
それでもどーしても納得できない時は、
”編集者と好みが違うんだな、私”
という最終理論で納得(笑)
実際、持っている楽譜より、グールドの演奏の方が、
腑に落ちることもときどきある・・・。
うーん、つくづくなまいきだなあ、私って。 -
今日、レッスンに行ったら、
突然先生が、
「3月でここの教室をやめて
自宅のあるM市でレッスンをするから
おいで。」
とのこと。
ええーっ。
先生は命ある限りこのO教室で教えると思っていたので
超心外。
というか、
びっくりしすぎてぼーっとしました。
なんにしても、
「もうここでは教えないから誰か別の先生に習って」と
見限られなくて、よかった。
それにしても、
今の先生には小学生の頃からずっと習っていて、
場所もこの場所だったので、
変わるのは小学校以来です。
ほえ~。 -
数日風邪をひいてめずらしく寝込みました。
健康のありがたさを実感しますね。
おかげでポカリスェットが大活躍ですが、
この、ボトルに貼ってある『乾燥上等』というシールは
なんなんだろ・・・
世露死苦な感じ?(古い)
全然関係ないけど、今日はNHKで日本庭園の庭師さんの
仕事ぶりを紹介する番組をやっていたので見ました。
無骨なおっちゃんが、大まじめに、大事なのは”愛”と何度も
言っていたのでびっくりした。
庭にはいろんな人がくる、悲しみを抱えた人も、喜びを抱いた人も、
そのみんなに安らぎなど感じてもらいたい、それが
彼の愛なのらしい(←うろ覚えですが)
はっきり”愛”が大切だって
言える人っていいな。
番組の司会者のブログまで追っていったら、
もっと突っ込んだおはなしが載っていた。
「10人中一人も賛成しなかったら、よっしゃ、
やったろうか、と思う。
10人中5人が賛成したら、ちょっと待てよ、
と思う。
10人中10人が賛成するようなものは、
絶対にやめとけと思う。」
「今思うのは、自分の立場を曲げないことは
いいとして、もっと周囲を説得すれば
良かったということです。
とにかく意を尽くして、ありったけの言葉を
用いて、自分の考えを説明するしかない。」
こ、こういうのを・・・
テレビでもっと紹介してくれたらいいのに。 -
曲名とか、作曲者を、覚えられないのは
どうやら遺伝のせいらしい。
親もそうでした。
でも、音楽は、”言葉”で表現できない領域を表現するんだから、
所詮曲名は、他の曲と区別するための認識票でしか
ないかな、と
負け惜しみをさらに言ってみたり
しかし、そもそも言葉って、
他のものとそのものを”区別する”、もしくは
”区別したなにかを共通認識として共有する・伝える”ための
道具なような気がする。狭い意味で。
そこに感情面など、見えない・触れないものも
加えて区別しようとした最初の人は偉い!
そのおかげで、言葉が大進歩しすぎて
最優先最大表現ツールになり、
重要になりすぎてるのは、
個人的になんとも残念ですけど。 -
クラシックCDも、なかなかお値段がお高いので、
割安な海外版を買ったりすることがあります。
すると、演奏者はもちろん、タイトルもぜーんぶ、
英語だったり(まだいい)、
ドイツ語だったり、
フランス語だったりして、
まったく、なんだか分からないわけで。
でも、それを疑問に思わないっていうか、
全然そのままにしておいて、平気な癖があるんですよ。
で、数年もたってから、
「うーん。この演奏家はなんて読むんだろう。」
とか(笑)
そこで登場するのが、Amazonでの検索。
同じCDの日本語版を探し出して、
「ほう、アレクシス・ワイセンブルクさんというのか。」
と、納得したり。
それどころか、
「これは『版画』、こっちは”なんちゃら博士”(注:ぐらどぅす・あど・ぱるなっすむ博士。こんなの舌かんじゃうですよ。)という
曲であったか。」
と、独り言言ってみたり。
それでいいのか・・・と
自分にツッコミ。
いいんだ。
ベルガマスク組曲を聴きたかったんだから(負け惜しみ)
それにしても、
ドビュッシーを聴く時は、いつもこのCDで、
いちばんこのアレクシスさんが気に入っているのに、
名前を知らなくて全然ふしぎに思わなかったなんて
わたしもつくづく、かわってるなー。
調べてみると、1970年に
パリ管弦楽団で
私の好きなおじいちゃん指揮者(待て。このときはまだ若いのか?)
プレートル(ジョルジュ・プレートル)と共演して、
ラヴェルやチャイコフスキーを演奏したらしい。
聴きたかった!(生まれてないけど) -
反則技だなあと思いつつ
音楽の泉には
「宇宙世紀の恋」のタイトルの方で
新曲を投稿しました。
midi制作者は、曲を作り、曲を編曲し、曲を聴き映え良くデジタル化し、曲を宣伝する役まで
一手に追わなきゃならないんだなー
と、
最近ぼんやり思っていたので。
曲の出来映えももちろん、クリックしてもらわないことには、
聴いてもらえない。
せこい考えだけど、困ったことです。
クリエイターさんも有名どころだと、
そのクリエイター名だけでクリックしてもらえるから羨ましいな。
でも今回は日本語にしてよかった。
先の投稿曲がずらっと英語名だったから、埋もれるところだった。
やれやれ。